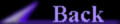

一向に進展しない交渉に飽いて、冨田肇(とみたはじめ)は視線を部屋の中に漂わせた。
原色の赤い絨毯にヤニの染み込んだ壁紙、中央に居座る大きな社長机。黒革のソファと部屋の隅に置かれた無駄に大きな胡蝶蘭の花瓶。地上10階のささやかな眺めを窓の外に期待しても、あとで建てられた隣のビルの外壁が視界を塞いでしまっている。最悪なのは、金色のけばけばしい額縁にはまった本人の写真が飾ってあることだ。フラッシュに反射したと思われる頭部の輝きが、目に眩しかった。
いつの時代のデザインだよと思いつつ、冨田は目の前にいる部屋の主・ダラス=ラッチマンに視線を戻した。赤毛のバーコード頭をしきりに直している姿を見ると、自分がここにいるのが馬鹿馬鹿しく思えてきた。
今から約1時間前…専用回線でラッチマンから電話がかかってきたのだった。『貴社の最重要機密を握っている。マスコミに流されたくなければこちらへ来い。…そうだ、妙な女を一人保護している。綺麗なうちに取りにくることだ。』そんな、時代劇のような内容だった。言葉どおりラッチマンの電機会社に訪れた冨田はしかし、まったくラッチマンの要求に応えようとしなかった。
「これが最後の通告です。彼女の身柄とデータCDを直ちに返してください。あなたが法外な方法を取っている以上、私としても手段は選べなくなりますよ。」
それに対し、ラッチマンはバーコード頭を整えてから言い返した。
「言っていることが理解できんね、ミスター・トミタ。手段はどうあれ、私はあなたの会社の根幹にかかわる機密を現在握っているんだ。要求をするのはこちらの方だ。経営の縮小と南部遺跡採掘権の半分の譲渡。それに…」
続けようとしたラッチマンの言葉は、不意に立ち上がった冨田に遮られた。
「もう通告はしました。失礼します。」
そう言って、すたすたと社長室の扉に向かって歩いていく。ラッチマンの顔がゆでだこのように赤くなった。
「き、貴様、私を馬鹿にしているのか! 状況が理解できていないのか!?」
冨田は無視した。歩みは止まらない。
「本当によかったのですか?あのままの勢いでデータCDを取り返すこともできましたが。」
ビルから出るとアギトが冨田に尋ねた。
「問題ない。どうせ中身はコンピュータウイルスのデータベースだ。下手に開くと即座に感染するし、何か問題があっても中央の弁護士にもいくつかコネがある。大丈夫さ。」
「…ジミー=ウォルトンにあのCD−ROMを渡したのはわざとですか?」
「コメントは控えよう。」
アギトは軽く礼をして押し黙った。冨田はアギトにだけは考えていることを教えてくれる。自分の茶髪を触り、改めてそれが不思議なことだと思った。
アーゼンの南部には旧文明の遺跡、いや、ゴミ捨て場だったと思われる場所がある。ゴミではあっても、貴重な金属類や古い電化製品などが手に入るため、そこを“採掘”して技術開発に役立てている。30年ほど前、ダラス=ラッチマンの会社・D&R社が、家電製品の復元に成功し独占市場になりかけていた所に、冨田の会社・ネフィス社が参入してきたのだ。情報機器類を主要製品にすえたネフィス社は急成長を遂げ、D&Rを追い抜いてしまった。今回の事件で冨田はD&Rを完全に潰すつもりなのだろう。
なぜ富田がD&Rを潰そうとするのか、理由は明白である。人種の問題なのだ。
アーゼンには2種類の人種が住んでいる。茶〜赤の髪、碧眼に褐色の肌を持つ“日”と呼ばれる人種と、黒い髪に黒い目、白い肌を持つ“月”と呼ばれる人種。不思議なことに、この2人種の間に子供ができることは無かった。生物として別の種なのだ。
“日”の人たちは自分たちが遺伝子操作の結果生まれた優良種だと主張している。事実、アーゼンの中の富裕層はほとんどが“日”に占められていた。そうした中で、“月”に対する偏見・差別が育つのも自然な流れだった。
D&Rはその典型ともいえる会社で、社員全てが“日”に統一されていた。その上独占権をフル活用させるので“月”の人たちの賃金水準では買えないような製品ばかりが作られる。当然、“月”の人たちからは嫌われていた。冨田もその“月”の一人である。
アギトは質問を変えた。
「では、なぜ来たのですか?」
少し微笑してから、冨田は答えた。
「ただの道楽だよ。――“彼女”を見に来たのさ。」